初音
谷崎潤一郎『吉野葛・蘆刈』
2017/04/08
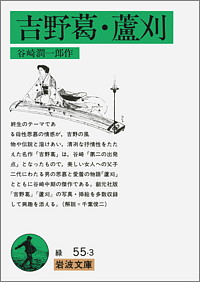 谷崎潤一郎の『吉野葛・蘆刈』をこの日ほぼ一日で読了。谷崎潤一郎はこれまであまり馴染みがありませんでしたが、先日、能「国栖」を観たことをきっかけにその周辺を調べていて本書に到達し、Amazonでポチった次第です。
谷崎潤一郎の『吉野葛・蘆刈』をこの日ほぼ一日で読了。谷崎潤一郎はこれまであまり馴染みがありませんでしたが、先日、能「国栖」を観たことをきっかけにその周辺を調べていて本書に到達し、Amazonでポチった次第です。
岩波文庫の表紙には、次のような短い紹介文が書かれています。
終生のテーマである母性思慕の情感が、吉野の風物や伝説と溶けあい、清冽な抒情性をたたえた名作「吉野葛」は、谷崎「第二の出発点」となったもので、美しい女人への父子二代にわたる男の思慕と愛着の物語「蘆刈」とともに谷崎中期の傑作である。
この説明のとおり、まず「吉野葛」は、東京に住む作家の「私」が一高時代の友人で今は大阪で旧家の若旦那におさまっている津村の誘いを受けて、上市から吉野川上流の国栖に入り、さらに南朝の後裔・自天王の旧蹟を訪ねた後に大台ヶ原から国栖へ戻る旅に出るという話で、その前半では「私」と津村とが国栖の里を目指す道中のゆかしい情景が谷崎の涼やかな美文で描写されるとともに、浄瑠璃「妹背川女庭訓」「義経千本桜」「芦屋道満大内鑑」や謡曲「二人静」への言及がなされますが、旅の第一の目的であった伝・初音の鼓を見るまでの道行的な展開から、中盤では津村による母恋いの1人語りが長々と続きます。幼い頃に失った母への思慕の情を募らせる津村は、祖母の遺品を整理しているうちに母が国栖の出であることを知り、ある日国栖への旅に出て存命であった母の親族に会うと共に、ゆかりのある紙漉きの娘を見掛けて、そこに母の面影を認めます。今回の「私」を伴っての国栖再訪の目的は、津村にとっての「初音の鼓」であるその娘への求婚が目的だ、というのが津村の説明でした。そのために数日国栖に滞在する津村を置いて「私」は自分の目的である歴史小説の題材取材のために吉野川上流への旅を継続し、三之公谷の険路に手を焼きつつ八幡平から隠し平までへの探訪を果たした後に入の波しおのはへ下り着きます。そこで「私」を出迎えたのは、くだんの娘を後ろに連れた津村でした。
私の計劃した歴史小説は、やや材料負けの形でとうとう書けずにしまったが、この時に見た橋の上のお和佐さんが今の津村夫人であることはいうまでもない。だからあの旅行は、私よりも津村に取って上首尾を齎した訳である。
明治末から大正初頃の吉野川上流を舞台とした紀行文としての面白さと共に、津村の口を借りて語る母への思慕とその形を変えた成就がある種の健康的な明るさで描かれて、心惹かれる一編でした。
一方の「蘆刈」は、夢幻能を見るような味わいがあります。その冒頭に置かれているのは、謡曲「芦刈」やその原典とされる『大和物語』からの次の和歌。
君なくてあしかりけりと思ふにも いとど難波の浦ぞ住みうき
摂津・岡本に住む主人公は、十五夜の日に思い立って後鳥羽院の離宮・水無瀬宮があったという淀川の山崎近くで月見をすることにし、淀川の中洲に渡ると蘆の中に腰を下ろして正宗を飲みながら白居易「琵琶行」を吟じたりいにしえの江口・神崎の遊女に想いを馳せたりしていました。すると蘆が揺れる気配がし、そこにわたしの影法師のようにうずくまっている男
がいて話しかけてきます。男は主人公に酒を勧め、自分も謡曲「小督」や「雨月物語」から江月照松風吹 永夜清宵何所為
(原典は「証道歌」)などを吟じましたが、主人公に問われるがままにやはり1人語りに入っていきます。こちらは、男の父が「お遊さま」と呼ぶ美しい未亡人への思慕を抱きつつその妹と結婚し、妹もまた夫の姉への思いを知って夫と姉を仲立ちしようとするものの、ついに結ばれることなくお遊さまは再婚し、やがて男の父も微禄して亡くなったという話。男は幼い頃から十五夜になると父に連れられてお遊さまの住む別荘へ向かい、月見の宴に興じるお遊さまの姿を生垣越しに飽かず眺めることが習慣となっており、今もこれから向かうところだと語り終えます。
わたしはおかしなことをいうとおもってでももうお遊さんは八十ぢかいとしよりではないでしょうかとたずねたのであるがただそよそよと風が草の葉をわたるばかりで汀にいちめんに生えていたあしも見えずそのおとこの影もいつのまにか月のひかりに溶け入るようにきえてしまった。
このように謎めいた終わり方をする「蘆刈」の文体は独特で、会話に「」をつけることなく地の文に溶け込ませ、しかもひらがなを多用して朦朧とした雰囲気を醸し出しています。話の構造に夢幻能の様式を当てはめるなら、主人公はワキ、男は前シテ、男の父は後シテということになりますから、男は実は男の父のお遊さまへの思慕が姿を現したものと見るのが最も素直ですが、男の父の生前からの執心がその子に受け継がれて晴らされることなく今に続いていると見ることもできそうですし、さらに男は誰の子なのかという疑惑も含め、曖昧さの中に余韻を残しています。
主人公の旅立ち、物語の舞台の情景描写と古典を紐解いての歴史叙述、もう1人の語り手による過去への回帰とそこで語られる女性への思慕、という共通する手法を用いたこれら二編は、前者が昭和6年、後者が昭和7年に発表されたもので、この時期は谷崎が関東大震災後の関西移住から数年後、最初の妻を佐藤春夫に譲って二番目の妻と再婚したものの、一方で松子御寮人(後の松子夫人)との恋愛関係が深まり始めていた頃に当たります。特に「蘆刈」のお遊さまははっきりと松子御寮人を念頭に置いて人物造形がなされていますが、そうした作家自身の事情と共に、畿内の豊穣な歴史風土がこれらの作品を谷崎に書かせたことは疑いありません。
ちょうど来月中旬には快慶の仏像を見に奈良へ行く予定がありますので、その際に「吉野葛」の舞台となった吉野川上流域を訪問することも検討してみたいと思います。