花束
ダニエル・キイス『アルジャーノンに花束を』
2000/02/26
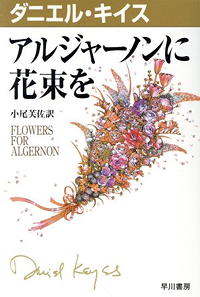 今週読んだのは『アルジャーノンに花束を』(〔著〕ダニエル・キイス〔訳〕小尾芙佐)。何年も前から読みたいと思っていましたが、文庫本、しかも字が大きくて読みやすくなっていたので、通勤のコートのポケットに忍ばせることにしました。
今週読んだのは『アルジャーノンに花束を』(〔著〕ダニエル・キイス〔訳〕小尾芙佐)。何年も前から読みたいと思っていましたが、文庫本、しかも字が大きくて読みやすくなっていたので、通勤のコートのポケットに忍ばせることにしました。
32歳になっても幼児の知能しかないチャーリイ・ゴードンは、ビークマン大学の実験台となって手術を受け、やがて驚異的な知能を獲得します。しかし、そこで彼が見い出したものは、母親の愛情を求めて報われなかった幼い頃の記憶や、優しくしてくれていると思っていた仲間の無慈悲な仕打ちの現実。そして、彼に先立って手術を受けていた白ネズミのアルジャーノンに起きた変化から、彼は自分が獲得した知的能力がやがて急速に失われていく運命にあることを知る、というストーリー。
物語は、プロジェクトに関わることになった3月3日から、超天才となった6月を経て、退行後のわずかに残された意識の中で精神遅滞者の養護学校へ赴くことを決意した11月21日までの、チャーリイ自身による経過報告として構成されており、文体がそのときどきの彼の知的レベルを反映しています。そして読者は、純真無垢なチャーリイの魂が智恵の目を通して見直すことになった過去や現在に傷つけられていくさまに悲しみを覚え、さらに、悲惨な結果となった自分の運命の受容をほとんど幼児語で書き綴った最後の1ページの独白に泣かされます。
ただし、知的障害を持つこと自体が悲劇なのではなく、いったん得た知的能力によって傷つき、それを失うことの自覚によっても傷つくという構造を理解しなければならない点には注意を要します。