打止
プログレナイト「Wish You Were Here」
2008/07/26
渋谷のDJバーEdgeEndで、プログレナイト「Wish You Were Here」。2月の「And You and I」に続く第2回です。DJはrobin☆、Hatch、それに私という前回同様の布陣(本当はゲストが予定されていましたが、直前に都合がつかなくなり、結局3人で回すことになりました)。
最初のセットのテーマは「変容」。プログレ王道バンドの、最盛期とは異なる姿を示したアルバムを集めたセットです。以下、曲名 / アーティスト名 / "アルバム名"(発表年など)。
The Score / Emerson, Lake & Powell / "Emerson, Lake & Powell" (1986年)
Emerson, Lake & Palmerの2人が、Asiaから足抜けできないCarl Palmerの代わりに同じ「P」のつくドラマー、Cozy Powellを迎えて制作したアルバム。アルバム自体は悪くなかったのですが、その後のツアーも含めて商業的には失敗し、このフォーマットは長続きしませんでした。オープニングナンバーの「The Score」はいかにもKeith Emersonという感じのゴージャスなシンセサイザーのフレーズが印象的で、某格闘技での入場曲にも使われたと記憶しています。
Take It Back / Pink Floyd / "The Division Bell" (1994年)
こちらはRoger Waters抜きの、つまりはDavid GilmourによるPink Floyd。邦題の『対』というのはジャケットからの連想かもしれません。作品の出来としてはよくも悪くもファンの期待どおり、つまりはよく計算された内容で、安心して聴ける、という言葉が似合います。しかしそれよりも、このアルバムの発表後に行われたツアーの模様を収めた映像作品『驚異』はまさに驚異的。光と音の洪水、という形容がよく使われますが、この作品を見た後では安易にその言葉を用いることがためらわれるでしょう。Pink Floydのファンでなくても、絶対に手に入れて欲しいものです。
The Power to Believe II / King Crimson / "The Power to Believe" (2003年)
21世紀すらを否定する曲でデビューしたKing Crimsonの、21世紀に入ってからの作品。私にとってのフェイバリットKCはJohn WettonとBill Brufordがリズム隊を組んだ1973年頃ですが、どのようなメンバーが参加しようと、中心にRobert FrippがいればそれはKing Crimsonなのですし、決して懐古趣味に走らず「進化するモンスター」と評されるその孤高の姿勢(作品でもライブでも)には畏敬の念を覚えます。
Heart / Yes / "90125" (1994年)
Steve Howeとはまったく異なるスタイルのギタリストTrevor Rabinが、Jimmy PageとのXYZ(eX-Yes, Zeppelin)プロジェクトの立ち上げに失敗し求職中だったChris Squire及びAlan Whiteと組んで立ち上げたバンドCINEMAが、商業的な理由からJon Andersonを迎えてYes名義で出したヒット作『90125』。随所に美しいアイデアが散りばめられた好アルバムで、この「Heart」は、その最後を飾る曲です。
Fading Lights/ Genesis / "We Can't Dance" (1991年)
Phil Collins Genesisのラストアルバム。Genesisはこの後にボーカルをかえてもう1枚のアルバムを出していますが、事実上の最終作と考えてよいでしょう。Peter Gabrielがバンドを離れてからすでに15年以上がたち、Genesisはポップバンドとして不動の地位を占めていたわけですが、この叙情的な歌詞をもつ曲には、まさにそのタイトルどおりプログレッシヴバンドとしてのGenesisの残照を感じとることができます。




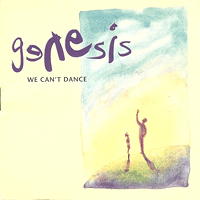
Hatch氏は、前半英語圏以外のプログレ中心、後半は王道=「21馬鹿」とか「月影の騎士」とか「闇の住人」とか。とりわけMike Oldfieldの『Discovery』収録の曲が極め付きの美しさ(後で早速Amazonで注文)。一方robin☆さんは、自身の事前コメントによれば「国内外のポストロック、アヴァンギャルドあたりです。基本、暗いです...。絶対に誰ともかぶらない自信があります」だそうで、確かに私のまったく知らない世界でした。
さて、事前に私のセカンドセットのリストを¥見たrobin☆氏は、とてもプログレとは思えない選曲にのけぞったそうですが、自分としてはRobert Fripp卿と同じく「私がプログレと呼べば、それはプログレである」というくらいの意気込みです。ただ、お客として参加していたMickyさんやいしこさん、じゅんこさんがHatch氏の選曲の一部に「それってプログレ?」と異議申し立てをし始めたのにはあわてて、横から「いや、プログレは何でもありです」と必死にフォローに回りました。
そういう地ならし(?)をした上で、robin☆さんのPink Floyd「Echoes」から引き継いだセカンドセットは、またも懲りずに「産業」セット。
Matte Kudasai / King Crimson / "Discipline" (1981年)
DISCIPLINEを名乗っていたバンドが、大人の事情で突如King Crimsonに変身。世間はあっと驚きましたが、ノスタルジーを横に置いて聴けばこれもなかなかいいじゃないか……というのが、80年代Crimson結成時の時代の雰囲気だったと記憶しています。もちろんRobert Frippの音楽だから凡百の産業ロックとは一線を画しているのですが、この曲に乗って太極拳を踊りたいといういしこさんのリクエストがあって、かなり変わったコラボレーションが実現しました。すてきなパフォーマンスを披露してくれたいしこさん、ありがとう!
Juke Box Hero / Foreigner / "4" (1981年)
Ian McDonaldらを脱退させて「4人」になったForeignerのこの作品が一部の曲にプログレの香りをたたえているのは、中心人物のMick Jonesの手腕もさることながら、「main synthesizers」としてゲスト参加したThomas Dolbyに負うところが大きい。「Waiting for a Girl Like You」のメインリフや「Urgent」での効果音が特徴的ですが、この「Juke Box Hero」でもイントロや曲間の静かなパートで滑り込む白玉や、コーラスでの遠い高音のフレーズなど、随所にセンスのよいシンセサイザーを聴くことができます。もちろん、静と動の大胆な対比もこの曲の魅力で、Dennis Elliottのドラミングはシンプルかつダイナミック。
Don't Let Him Go / REO Speedwagon / "Hi Infedility" (1980年)
REOのこのアルバムは、実によく売れました。その原動力は、2曲目に収録された美しいバラード「Keep On Loving You」であったでしょうが、自分としてはオープニングナンバーのこの曲を推したいところ。フィードバックギターがフェードインしてきて重たいリズムが合流し、Kevin Croninの特徴的なボーカルが始まります。そして間奏でのNeal Doughtyのシンセサイザーソロはこのバンドにしては珍しく技巧的、といった具合にいろいろなアイデアが盛り込まれた聴き応えのある曲になっています。
Don't Look Back / Boston / "Don't Look Back" (1978年)
Bostonはプログレか?これはかなり微妙な問いですが、どうしても肉食人種のアバウトさを想起させるアメリカンハードロックにはあるまじき、緻密な構成と練りに練ったギターの音質は、このバンドをある種特別な地位に就かしめています。そのイメージは、MITで電気工学を学んでいたというギターのTom Scholzのインテリジェンスに負うところ大……というより、Bostonはもともと彼のワンマンプロジェクトで、デビュー作のプロモーションツアーのためにバンドメンバーを集めたと言われており、凝り性のTomの性格のために極端な寡作であることもよく知られています。この『Don't Look Back』は彼らの2作目、そしてタイトルナンバーのこの曲は、印象的なギターのフレーズが一度聴いたら二度と忘れられないほどのインパクトをもっています。
Fooling Yourself (The Angry Young Man) / Styx / "The Grand Illusion" (1977年)
StyxといえばDennis DeYoung(vo,k)のハイトーンボーカルが売りですが、ギターのJames YoungとTommy Shawもかなりの割合でリードボーカルをとっており、ポップセンス溢れるこの曲はTommy Shawがアコースティックギターを弾きながら歌っています。とはいいながら、この曲を特徴づけているのはやはり大胆に導入されているシンセサイザーで、特にシンセサイザーソロで聴かれるゆったりした7拍子のリズムは、ポップスとプログレとの幸福な融合という感じがします。
The Pitchman / Saga / "Heads or Tales" (1983年)
あまりに産業色に染まった甘い選曲が続いたので、ちょっとスパイスをきかせる意味でSagaのこの曲をここにもってきました(上述のアンチョコでは、ここにはTotoが入る予定でした)。これは正解だったようで、おっ、これは?という感じの反応が見られてうれしい。私自身もかけてみて再認識しましたが、「産業」と「プログレ」とでは通底する緊張感が全然違います。カナダのプログレッシヴポップバンドSagaは私のフェイバリットグループの一つで、同じカナダのRushともども、北米・ヨーロッパでの人気と日本国内での評価が乖離しているよい例。これからもコンスタントにとりあげたいバンドです。
Frontiers / Journey / "Frontiers" (1983年)
Jonathan Cain(k,g,vo)を迎えて大ヒットアルバム『Escape』を世に送り出したJourneyが、Jonathanのシンセサイザーを全面的に押し出して制作した傑作アルバムの、タイトルナンバー。このアルバムは素晴らしい出来映えで、バラエティーに富んでいて、しかも一曲たりとも捨て曲がありません。そうした中でもこの「Frontiers」はかなり異色の曲で、奇妙奇天烈なドラムのリズム、Prophet-5とJupiter-8を駆使した凝ったシンセの効果音など、実験的と言ってもいいくらい斬新でありながら、楽曲としての魅力を損なっていません。以前robin☆さんがこの曲を『Shining Star』でとりあげたことがありましたが、今回ぜひともプログレという文脈の中でこの曲を紹介してみたくて選曲しました。
Heat of the Moment / Asia / "Asia" (1982年)
上述のアルバム『Frontiers』では、「Frontiers」に続いて荘厳なギターのパワーコードが鳴り響き、ラストの「Rubicon」になだれ込みます。このパワーコードの連想から、産業シリーズの最後はAsiaの大ヒット曲「Heat of the Moment」。この曲に関しては、もはや説明の必要はないでしょう。今年5月のオリジナルメンバーによるAsia来日公演では『Asia』全曲演奏が行われてファンを驚喜させましたが、アルコール中毒に蝕まれて十分なパフォーマンスができなかった頃のJohn Wettonをファンが見捨てなかったのも、いつか彼が健康を取り戻して、もう一度この曲を最高の演奏で聴かせてくれるはず、という期待があったからです。
アジアの純真 / Puffy / "amiyumi jet fever" (曲:1996年)
最後の曲として用意していたのは、パフィーのデビュー曲。お気付きのように「アジアつながり」というベタな選曲ですが、しかし、奥田民生作曲のこの曲の輝かしい曲調はElectric Light Orchestraへのオマージュだし、井上陽水のペンになる歌詞はノリはよくても意味不明、まさにJon Andersonの世界ではないでしょうか。






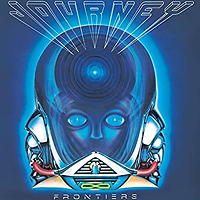


ともあれ以上で、この日のイベントは終了。集まってくださった皆さん、本当にありがとうございました。果たしていつになるかわからないけれど、次回もお楽しみに。今回はタイミング的に集客に苦労してしまったけれど、次回は十分に考慮してより多くの人に参加していただけるようにしたいもの。でも、さすがにもう産業は打ち止めかな。