数寄
白洲正子『西行』
2014/05/24
 白洲正子さんの『西行』を読了。これは『芸術新潮』の連載を1988年に単行本化したもので、西行(1118-1190)の生涯をおおむね時系列で追っているから伝記であり、歌を詞書と共に読み解くところに力点があるので歌論の側面もあり、その足跡を辿るために訪れた各地を紹介する紀行文でもあり、といかにも白洲正子さんらしいカオスを独自解釈で一つにまとめる豪腕がまたしても冴えわたった本でした。
白洲正子さんの『西行』を読了。これは『芸術新潮』の連載を1988年に単行本化したもので、西行(1118-1190)の生涯をおおむね時系列で追っているから伝記であり、歌を詞書と共に読み解くところに力点があるので歌論の側面もあり、その足跡を辿るために訪れた各地を紹介する紀行文でもあり、といかにも白洲正子さんらしいカオスを独自解釈で一つにまとめる豪腕がまたしても冴えわたった本でした。
その最初に取り上げられた歌はこちら。
そらになる心は春の霞にて 世にあらじともおもひ立つかな
俵藤太秀郷の家系に連なる「重代の勇士」として颯爽と駿馬を駆けさせ、
伏見過ぎぬ岡の屋になほ止まらじ 日野まで行きて駒試みん
などと若々しく歌った北面の武士・佐藤義清が23歳で出家した理由については諸説あるようですが、『源平盛衰記』は申すも恐ある上﨟女房を思懸け進らせたりけるを、あこぎの浦ぞと云ふ仰を蒙りて、思ひ切り
出家を決心したと伝えており、著者はこの申すも恐ある上﨟女房
こそ待賢門院璋子(1101-1145)であって、西行は待賢門院を「永遠の女性」として熱愛したと断言しています。待賢門院は養父・白河院の異常なまでの寵愛のもとに育ち、長じて鳥羽帝の中宮として崇徳・後白河両帝の母となりましたが、成人前から素行に噂があったばかりか、崇徳帝は白河院の胤であるとも噂された人。17歳も年上の女性にのめりこもうとする妻子ある若武者に向けられた「あこぎの浦」とは、禁漁の阿漕浦に禁を破って夜な夜な網を引いていた漁師が発覚して海に沈められたという哀話を下敷きに、禁断の逢瀬が重なれば人の噂にものぼるだろうという警告です。このように(著者の説によれば)悲恋がもとで若くして出家した西行は、法体になったからといって仏道に専心するのでもなく、都にとどまったまま友人たちや知り合いの女房たちとの交流の中で自由気ままな暮らしを続けていたようです。
世中を捨てて捨てえぬ心地して 都離れぬ我身なりけり
著者もまた、この時期の西行を追って嵯峨野から大原野を辿り、謡曲「西行桜」の舞台となった勝持寺などを紹介していますが、やがて30代の西行と共に著者の足は花の吉野へ向かいます。
吉野山こぞの枝折の道かへて まだ見ぬかたの花を尋ん
吉野を舞台として、花の美しさを讃えその散るさまを惜しむ歌を数多く歌った西行にとって、吉野に籠ったのは待賢門院への思慕から解放されるためであり、それでいて桜の花に女院の面影を見続けていたというのが、著者の説。この文脈からすると、あたかも西行の辞世のように思われている次の歌も、先に亡くなった待賢門院への久遠の愛を歌ったもののように思えてきます。
ねがはくは花のしたにて春死なん そのきさらぎの望月の頃
大峯の修行、熊野詣を経て著者の筆が唐突に大磯から那須野を越えて平泉にまで飛ぶのは、西行が生涯に二度、奥州への旅に出ているからですが、那須野では西行の
道のべに清水流るる柳陰 しばしとてこそ立ちどまりつれ
を芭蕉が翻案した
田一枚うゑてたちさる柳かな
に、むしろ圧倒されました。暫しと立ち止まったところ思わず時を過ごしてしまい、気がつけば田が1枚植えられていた、という説明(引用)によって、西行の歌が時空を超えて親しまれてきた歴史を垣間みるとともに、三十一文字を十七文字にさらに凝縮してみせる芭蕉の感性の鋭さには脱帽するしかありません。
著者の紀行は、摂津の江口、高野山を経て、崇徳院の配流先となった讃岐への旅に多くの紙数を割き、ついで高野山を出て西行が移り住んだ伊勢に移ります。伊勢神宮の内宮にて読んだ歌。
この春は花をおしまでよそならん 心を風の宮にまかせて
この頃、西行はすでに60代。かつて春風の花を散らすと見る夢は さめても胸のさわぐなりけり
とまで歌った花(待賢門院)への強い思慕からようやく解き放たれて安らかになった西行の心境が見てとれます。こうしていよいよ老境に差し掛かった西行が、東大寺再建の勧進のために平泉への2度目の旅に出たのは、69歳のとき。
年たけて又越ゆべしと思ひきや 命なりけりさやの中山
よもや再び小夜の中山(静岡県掛川市)を越えることがあろうとは、という詠嘆の中に命なりけり
の絶唱が鋭く差し挟まれ、読む者の胸を突きます。そして、この旅での次の歌が、おそらくは遠からず訪れるであろう人生の終焉を意識しつつ歌われたもの。
風になびく富士の煙の空に消えて ゆくへも知らぬわが思ひかな
上の句に字余りを二度も重ねた破調であっても、下の句の諦観の大きさが深い余韻を残す歌だと思いますし、こうしてみると、花への執心を連綿と綴ったようなあのねがはくは
の歌よりもこちらの方が、確かに辞世としてふさわしいようにも思えてきます。こうして西行の生涯を、その足跡を辿りながら歌と共に旅した著者は、最後に次のように述べて筆を置いています。
西行の真価は、信じがたい程の精神力をもって、数寄を貫いたところにあり、時には虹のようにはかなく、風のように無常迅速な、人の世のさだめを歌ったことにあると私は思う。
ここで「なるほど、そうだったのか。いい本を読んだなあ」と納得してしまえば簡単なのですが、ちょっと待て。白洲正子さんの本をこのところ立て続けに読んでわかってきたのですが、きっとこれは白洲正子さんの中だけの西行であって、西行本人がこの本を読んだら、もしかすると異議申立てをするかもしれません。というわけで、引き続き西行関連の本を漁ることにしてAmazonで以下の本を買い求めました。
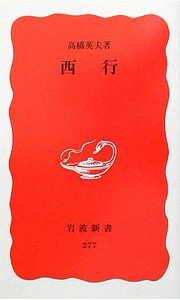


ただ、いっぺんに三冊というのはちょっと調子に乗りすぎてしまったかもしれません……。