空海
高村薫『空海』
2015/12/09
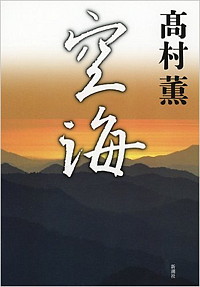 〔著〕髙村薫『空海』を読了。この本は、国立劇場で雅楽「盤渉参軍」を聴いた後に半蔵門駅の上の書店に何の気なしに入ったところで目に付いたのを衝動買いしたものですが、それはもちろん、今年の高野山旅行以来の空海に対する関心がベースにあってのことです。
〔著〕髙村薫『空海』を読了。この本は、国立劇場で雅楽「盤渉参軍」を聴いた後に半蔵門駅の上の書店に何の気なしに入ったところで目に付いたのを衝動買いしたものですが、それはもちろん、今年の高野山旅行以来の空海に対する関心がベースにあってのことです。
髙村薫と言えば、『マークスの山』などのサスペンスや『新リア王』などの実験的かつ重厚な社会派の作品を生む寡作の作家という印象がありますが、本書は共同通信社が2014年4月から2015年4月まで配信し各種地方紙に掲載された『21世紀の空海』に加筆してまとめたもので、伝記の要素もあれば紀行文の要素もあり、宗教論でも社会批評でもあるといった多元的な内容になっています。新聞に連載されることを想定して書かれたものだけに、文体は読みやすく、また高野山をはじめ空海ゆかりの地の写真が豊富に使われています。
室戸岬の洞窟で百万回の真言の後に明星来影の神秘体験を得た若き修行者、唐に渡ってわずか2年で恵果阿闍梨から伝法灌頂を受けた天才学僧、密教の秘儀をもって鎮護国家の修法を執り行うカリスマ司祭。両界曼荼羅の世界に住み数々の著作を残す偉大な宗教家となった空海の事跡を辿った著者は、さらに満濃池の修築工事や綜藝種智院の創設をもって衆生の尊崇を集めた社会事業家としての空海にも着目していますが、その空海が真言密教の根本道場として日本の青龍寺とみなしたのは東寺(京都府)であり、かたや空海が高野山で過ごした年月は意外に短かったという本書の指摘は、私にとって予想しなかった事実でした。
しかし今や、空海と言えば高野山。それはなぜなのか?
空海が弘法大師の諡号を受けたのは、その死後87年目のこと。筆者は、空海の名声が比較的早い時期に下火になってしまった後、教団の維持と経営のために東寺が空海を本尊にした御影供を行い、高野山の御廟での入定留身説話を広めることによって空海を神格化した経緯を明らかにしています。そこでは、宗教家・空海の著作や教義は研究の対象とはされず、生前の空海とは断絶した信仰の対象としての空海像が立ち上がりました。高野山自体も、真言密教の奥義を探究する修行の場から大師の御廟を守る浄土信仰の霊場に変貌し、さらに高野浄土を説いて各地を回った高野聖の存在が高野詣を庶民の間に広めていきます。
筆者の視線はさらに、民衆の中に空気のように溶け込んでいった弘法大師の姿を、現世利益にフォーカスした各地の不動尊信仰や、お大師さまと同行二人で歩む四国の遍路道の中に追い、再び高野山に戻って、大師信仰でも宗祖空海への尊崇でもなく、それ自体が漠とした祈りの対象となって存在している
高野山の今を眺めます。
結局、筆者の見るところ空海の入滅後、百年を経ずして東寺が空海その人の肖像を祀り始めたとき、あるいは弘法大師の諡号の下賜とともに空海は御廟でなおも生きているとする入定留身説が作られたとき、歴史上の僧空海の残像は自然消滅し
たのであり、空海を失った真言宗はその後、弘法大師を尊格とする庶民信仰と、国家鎮護と朝廷や皇族の息災を祈る国家宗教と、さらには日本総菩提所としての高野浄土の三つの顔で千二百年を生きてきた
のだということになります。後の世に登場した鎌倉六宗がいずれも空海と交流のあった最澄に由来する天台宗から生まれたことも、偉大過ぎる空海が完成させた教義の体系を空海没後ほとんど更新することができなかった真言宗に対して、密教を消化する時間がなかった最澄が理論の発展を後継者に委ねたことによって変遷と進化を持続した天台宗の伝統のなせるわざ。そして筆者は、即身成仏の深遠な教義と浄土信仰や現世利益とがかけ離れてしまっている現代の真言密教に対してそれでもいいのかもしれない
といったんは理解を示すものの、最後に生きた空海その人に会ってみたい
と歴史の彼方に目を向けて筆を置いています。
たまたま書店で手にとったのが空海の人物像へのアプローチとして好適な本書であったことは幸運で、昨年の春に西行について固め読みしたように、ここを起点にしばし空海を追いかけてみようかとも思わされました。しかし実は、すでに「積ん読」状態になっている本が何冊もあり、空海に立ち戻るのはしばらく先のことになりそう。そして明日から読むことにしているのは、前々から一度しっかり把握しておきたいと思っていたテーマ「ポル・ポト」です。