宮廷
大高保二郎『ベラスケス』
2018/08/23
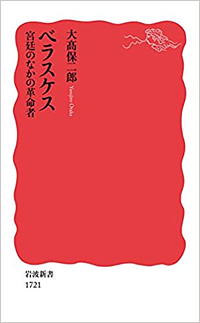 〔著〕大高保二郎『ベラスケス』を読了。
〔著〕大高保二郎『ベラスケス』を読了。
先日上野で「プラド美術館展」を見たことに触発されて、まとまったかたちでベラスケスの事績を学んでみようと読み始めたものですが、美術館での展示が時系列ではなく主題別に作品を並べ、ベラスケスのみならず17世紀当時のスペイン宮廷にまつわる作品も広範にとりあげたものであったのに対し、本書ではベラスケスの誕生から死までを順を追って解説しているので、ベラスケスその人の生涯を知るには好適でした。
若くして国王付きの画家となり、廷臣としても栄達を遂げていったベラスケスは、その活動のほとんどが閉鎖された宮廷の中での公務であり、国庫を傾けてまでも宮殿を古典古代や当代の一流美術品で飾ろうとする国王フェリペ4世の下、いわば空間デザイナーとして忠実にその職務を果たし続けた公人としての記録ばかりが残されています。しかし著者は、
- 美談のように伝えられているルーベンスとの関係には実は確執もあったであろうこと
- 第二次ローマ滞在が長引いた理由は当地にできた愛人の出産を待っていた可能性があること
- 長年にわたる奉仕の背後にコンベルソ(ユダヤ教徒から改宗したキリスト教徒)の家系に生まれた自身の出自の克服がもくろまれていたこと
- 「慰めの人々」(宮廷に仕えた矮人や障害者)への公平な眼差しにもそうした出自が影響したであろうこと
- そして、傑作「ラス・メニーナス」こそ、克服の仕上げとなるサンティアゴ騎士団への入団(=貴族としての地位の獲得)に向けた
王手
であった可能性があること
などなどいくつもの新たな視点を提供し、人間ベラスケスの姿を血の通ったものにしていて、大変興味深く読み進めることができました。
また本書を通じて、改めて17世紀のスペインの歴史を学び直すことになりました。
当時のスペインは、レコンキスタ〜大航海時代の栄光がすでに過去のものとなり、三十年戦争における事実上の敗北により斜陽の一途を辿るばかり。しかも、ハプスブルク家は貴種であるがゆえの数世代にわたる近親婚により遺伝的な脆弱性を負ったこともあり、フェリペ4世の子供たちの多くが早逝している中、かろうじてつつがなく成長した愛娘マリア・テレサを「キリスト教世界全体の平和の実現」のため戦争相手であったフランス・ブルボン家の太陽王ルイ14世に嫁がせなければならなかった国王の悲哀も、本書は国王の告白として紹介しています。ところが皮肉なことに、ルイ14世とマリア・テレサの婚儀のための遠征旅行を取り仕切ったベラスケスはその過労がもとでほとんど突然死のように亡くなり、しかも婚儀に際しての約束(=和平の条件)であった持参金をスペイン王室が支払いきれなかったことが後にブルボン家がスペインに対する王位継承権を主張してハプスブルク家にとって代わる大義名分を与えてしまいます。こうして見ると、本書のもう1人の主人公はフェリペ4世であり、あるいは悲運の王に代表されるスペインそのものであると読むこともできるかもしれません。
 ともあれ、先日の「プラド美術館展」で感じたスペインに対する関心が、本書を読むことによってますます高まったことは間違いありません。いつの日かマドリードのプラド美術館を訪ねて「ラス・メニーナス」をこの目で見ることが一つの目標になりました。
ともあれ、先日の「プラド美術館展」で感じたスペインに対する関心が、本書を読むことによってますます高まったことは間違いありません。いつの日かマドリードのプラド美術館を訪ねて「ラス・メニーナス」をこの目で見ることが一つの目標になりました。
最後に、本書で紹介されていた面白いエピソードを一つ。夏目漱石の『三四郎』の中に、三四郎や美禰子が足を運んだ展覧会で暗い肖像画の模写が展示されており、これを見た画家の原口が「どうも、原画が技巧の極点に達した人のものだから、旨く行かないね」と批評する場面がありますが、この肖像画は先日の「プラド美術館展」に展示されていた「メニッポス」で、実際に明治41年春の第6回太平洋画会展に出品されたものを夏目漱石が目にしたことがこの描写に活かされた模様。すでにその時期の日本でもベラスケスの評価が高かったことを示すエピソードですが、それにしても漱石は……
と著者は謎かけをしています。技巧の極点に達した人
というベラスケス像をどこで培ったのであろうか