統治
『リー・クアンユー回顧録』
2001/01/18
東南アジア最強の政治家、シンガポールのリー・クアンユーの回顧録を、ほぼ2カ月をかけて読み終えました。上下巻で合わせて1,000ページの大著ではありますが、通勤の行き帰りや休日の一部をあててゆっくり読み進めても、一つ一つのエピソードが極めて印象的で倦むことがありませんでした。
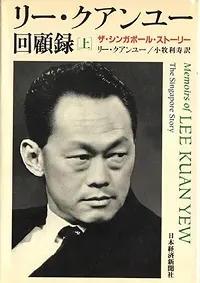

リー・クアンユーは1923年にシンガポールに生まれ、英国 / 日本の統治下に育ち、ケンブリッジ大学で法律を学んで50年にシンガポールに戻ってから弁護士を開業。54年に人民行動党を創立し、59年にシンガポール自治州の初代首相となって63年のマレーシア独立に参画したものの、65年にマレーシアから追い出されるようにシンガポールを独立させることになりました。その後、敵対的な周辺国に囲まれながら何の資源ももたない(水すらもマレーシアからの供給に頼っている)シンガポールを長期にわたり率いて、同国を国民1人当たりGDPが世界でも上位10か国に入る先進国に育て上げた後、90年に首相を退いて現在は上級相をつとめています。本書の上巻は、シンガポール在住の華人の子として生まれた著者が、日本軍政下での暴力の恐怖を経験して統治の本質に目覚め、大英帝国の教育システムの中で英国の植民地支配からの独立を志向するに至り、帰国後労働組合の弁護活動を通じて共産勢力と不即不離の関係を保ちながら政治の世界に足を踏み入れていき、ついにはマレーシア独立を勝ちとるものの、マレーシア政府のマレー人至上主義との対立の中で不本意な独立(分離)を余儀無くされるまでを時系列を追って回想し、下巻は独立国シンガポールの35年間の歩みを国内情勢と外交とに分けてテーマごとに記述しています。
リー・クアンユーという統治者の強靱な意思と高い知性は、本書に記されたさまざまなエピソードの中のいたるところに描かれています。例えば彼は、英語をネイティブとする環境で生まれ育ち、ケンブリッジで首席をとるほど英国の制度と文化に親しみながら、他民族国家であるシンガポールで政治家として活動するために、第2言語であったマレー語に加えて北京語と福建語を学び、ついにそれらのいずれの言語でも自由に高度な演説と議論を展開できる能力を身につけます。とりわけ、中華人民共和国が東南アジア世界へ共産主義の価値観を発信し続けていた1960年代には、英語を解さない華人層を中国語で導くことは国家の成否にもかかわる重要課題であったからです。また、マレー人至上主義(ブミプトラ)を標榜するクアラルンプールとの確執と民族対立、そのマレーシアに対するインドネシアの対決政策(コンフロンタシ)、シンガポールの安全保障と経済を支えてきた英国のスエズ以東からの撤退、ソ連の支援を受けた北ベトナムの拡張とカンボジアへの侵攻による東南アジア世界の動揺、さらには近年の東アジアを襲った通貨危機に至るまで、シンガポールの歴史は絶えることのない苦闘の歴史というほかはありません。そうした中で、リー・クアンユーは徹底した能力主義と儒教的倫理を基盤に、清潔で効率的な政府を作り、勤勉な国民性を培い、巧みな外交政策によって安全保障を確保し、先進諸国の投資を招き寄せていきます。下巻の原題「From Third World to First」は、まさに彼の超人的な努力が成し遂げた奇跡を端的に表現していると言えるでしょう。
同時に、リー・クアンユーの31年間にわたる統治が実現した政策の一貫性が、この書のもう一つの原題である「The Singapore Story」の本質であったように思います。彼の人生とシンガポールの歩みとは、まさに表裏一体のもの。ややもすれば西側メディアから管理国家と批判を受けるシンガポールのこの統治スタイルも、リー・クアンユーに言わせれば、西洋型の民主主義が成り立つためには一定の段階に到達した経済と国民の教養レベル、中流層の形成により価値観を共有する市民社会の存在が前提条件として必要であり、そのような歴史的・文化的パターンを歩んできてはいない国々(例えば多くの旧植民地諸国)に米国流リベラルの常識は当てはまらないということになります。確かにマルコスのフィリピンやスハルトのインドネシアのように、それは一歩間違えれば腐敗の温床となる危険を孕んでいますが、シンガポールという国のコンパクトさと地政学的なポジションが、彼自身の資質とあいまって、安定した統治組織のもたらすメリットを極大化してきたのだといえるでしょう。それは、東アジア地域において最も強大な影響力を行使し、今後もその関係性がこの地域の政治・経済の安定と発展を左右する米・中においてすら実現してこなかったことでもあります。4年に一度大きく政策がぶれるアメリカ、文革から開放政策へと怒濤のような体制の変転を経過してきた中国。そしてもちろん、長きにわたりリーダーシップの欠如に苦しむ日本においても。