楼蘭
長澤和俊『楼蘭古城にたたずんで』
2001/03/03
タリム盆地の東端にあって、シルクロードの北道(天山南麓)と南道(崑崙北麓)の分岐点にあたる都市・楼蘭の名は、「さまよえる湖」ロプ・ノールとともに10代の頃に学校で習い、その後読んだ井上靖の小説『楼蘭』でイメージを膨らませていました。
楼蘭(原音はクロライナ)地方に東西交易の隊商用の補給地兼「玉」の交易場としてのオアシス国家が形成されたのは今から3500年ほど前ですが、その名前が初めて文献に姿を現わすのは前漢の文帝の4年(紀元前176年)、匈奴の冒頓単于が文帝にあてた手紙の中でのこと。ここからわかるように、楼蘭は漢と匈奴の両大国の政治的・軍事的な圧迫の下に、あるときは匈奴に人質を差し出し、あるときは漢に朝貢して国家の生存を図っていました。紀元前77年、親匈奴派の楼蘭王・安帰が漢の大将軍霍光の派遣した刺客に暗殺され、その後に親漢派の弟・尉屠耆が据えられると共に、「楼蘭」は国名を「鄯善」と改めさせられ、漢の傀儡王国と化していきます。しかし、後漢の明帝の時代に西域に30年以上も赴任していた西域都護の班超が西暦102年に洛陽に戻ると間もなく、漢は西域経営から手を引き、この地にはカニシカ王で有名なクシャナ朝の影響が及びます。クシャナ朝がササン朝ペルシアに滅ぼされたことで独立を回復したのもつかの間、今度は中国の晋が進出し、さらに五胡十六国時代の政治的混乱の中で人口は激減して、7世紀前半には楼蘭人たちはこの地を放棄し、以後忘れられた都市となっていったようです。
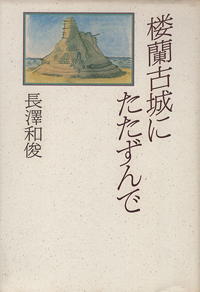 しばらく前に高円寺の古本屋で入手した〔著〕長澤和俊『楼蘭古城にたたずんで』は、楼蘭研究を続けてきた筆者が日中共同探検隊に加わって、大変な苦難の末に楼蘭遺跡を訪れた旅の記録を中心に、楼蘭の歴史についても解説した本。淡々としていながらどこかにユーモアを含んだ文体の中に、長年の憧れだった楼蘭を訪問できた感動が伝わってくる好著でした。しかし、本書で紹介された楼蘭の実相と井上靖の『楼蘭』との間には、極めて大きな齟齬がありました。
しばらく前に高円寺の古本屋で入手した〔著〕長澤和俊『楼蘭古城にたたずんで』は、楼蘭研究を続けてきた筆者が日中共同探検隊に加わって、大変な苦難の末に楼蘭遺跡を訪れた旅の記録を中心に、楼蘭の歴史についても解説した本。淡々としていながらどこかにユーモアを含んだ文体の中に、長年の憧れだった楼蘭を訪問できた感動が伝わってくる好著でした。しかし、本書で紹介された楼蘭の実相と井上靖の『楼蘭』との間には、極めて大きな齟齬がありました。
まず、井上靖の『楼蘭』で繰り返し登場するイメージは「流砂に埋もれゆく都・楼蘭」というものですが、実際の楼蘭地方は砂漠ではなく沙漠、より具体的にはヤルダンと呼ばれる風化土堆群に囲まれています。さらに決定的なのは、井上靖の『楼蘭』では尉屠耆が王位に就いて鄯善に国名が変わったとき、漢の政策により楼蘭は国民をあげて別の地に移住させられたものとしており、このことによる世代を超えた望郷の念がこの小説の重要なモチーフになっていることです。実は、この見解は中国の研究者の間では一般的な見方で、移動後の鄯善は現在のミーランに擬せられているのですが、長澤氏の見解によればこれは大きな誤解で、文献学的にも考古学的にも、楼蘭=鄯善と考えるのが正しいようです。
玄奘三蔵が唐への帰途を歩んでいた西暦644年には、楼蘭王国の版図にあった南道の各オアシスはまったく荒廃して、人煙断絶した廃虚と化していたことが記録に記されています。その後、長きにわたり地上から消えたと思われていた楼蘭は、西暦1900年にスウェン・ヘディンによって見い出されました。しかしその際の測量図と、長澤氏が訪れた1988年の楼蘭との間でも、すでに著しい荒廃の進行が見られたそうです。今ではロプ・ノールもすっかり干上がってしまい、強烈な風化作用がわずかに残された仏塔や三間房、城壁などを着実に侵食していきます。東西交通の要衝に豊かな交易都市として栄え、さらには1500年の眠りから一度は目覚めた楼蘭は、さほど遠くない未来に今度こそ本当にその痕跡を失ってしまうのかもしれません。