萩原
『萩原朔太郎詩集』
2001/09/30
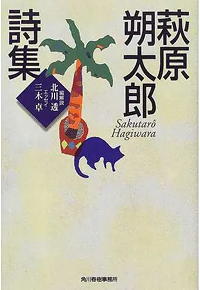 初めて萩原朔太郎の詩集を買って読んだのは中学生の頃でしたが、そのときはその暗く救いのない詩に共感できず、やはりというか何というか、より平明で美しい(と思えた)中原中也の詩世界に傾倒していったのでした。それから月日は流れ、最近ふと書店で見掛けた文庫本の『萩原朔太郎詩集』(ハルキ文庫)を買い求めて会社の行帰りに読み通していったのですが、30年前に読んだときとは印象が一変しているのに、我ながら驚いてしまいました。
初めて萩原朔太郎の詩集を買って読んだのは中学生の頃でしたが、そのときはその暗く救いのない詩に共感できず、やはりというか何というか、より平明で美しい(と思えた)中原中也の詩世界に傾倒していったのでした。それから月日は流れ、最近ふと書店で見掛けた文庫本の『萩原朔太郎詩集』(ハルキ文庫)を買い求めて会社の行帰りに読み通していったのですが、30年前に読んだときとは印象が一変しているのに、我ながら驚いてしまいました。
萩原朔太郎の初期の詩には、日本語の表現力がそれまでの誰もが想像もしなかった程に豊饒であることを提示してみせた作品が多く、言葉の選択やリズムにはっと胸を突かれます。例えば有名な『竹』の2連目。
かたき地面に竹が生え、
地上にするどく竹が生え、
まっしぐらに竹が生え、
凍れる節々りんりんと、
青空のもとに竹が生え、
竹、竹、竹が生え。
こうして横書きにすると若干印象が変わってしまいますが、画数の少ない「竹が生え」の繰り返し、「かたき」「するどく」といった形容、微妙に定型をはずしたリズム、口語と文語の混合などが、地面からさまざまな太さで頭上へと伸び上がっていく竹林を視覚的にも連想させる。これだけだと高村光太郎の世界になってしまいそうですが、この前の1連目にうたわれている「青竹の地下にあってかすかにふるえている根の先の繊毛」は現代人の神経の病みをイメージさせ、このモチーフは饐えた菊、屋根の上で「おわああ、ここの家の主人は病気です」と泣く黒猫、内臓がくさりかかった蛤、といった具合にさまざまにかたちを変えて繰り返され、読む者を不安にします。
セクシュアルな欲望を表現した詩も少なくなく、女性の柔らかい手や乳房への憧憬が、あるときはストレートに(『愛憐』)、あるときはユーモラスに(『その手は菓子である』)表現されますが、それらのどこかに狂気の毒が含まれていると感じるのは、これらの詩を書く同じ詩人が例えば『春の感情』の中で次のようにうたって見せているためです。
春がくるときのよろこびは
あらゆるひとのいのちをふきならす笛のひびきのやうだ
ふるへる めづらしい野路のくさばな
おもたく雨にぬれた空気の中にひろがる一つの音色
なやましき女のなきごゑはそこにもきこえて
春はしっとりとふくらんでくるやうだ。
春としなれば山奥のふかい森の中でも
くされた木株の中でもうごめくみみずのやうに
私のたましひはぞくぞくとして菌を吹き出す
また萩原朔太郎の言葉に対する独特な感性は、猫の泣き声おわあ、こんばんは
蠅の羽音ぶむ ぶむ
犬の遠吠えのをあある とをあある やわあ
などに見てとることができ、『軍隊 通行する軍隊の印象』ではづしり、づしり、ばたり、ばたり / ざつく、ざつく、ざつく、ざつく。
と繰り返される行進の足音によって、油ぎった巨重の機械に喩えられた軍隊の暴力性が読む者の眼前を通過しているかのような錯覚すら覚えさせます。