講義
長澤和俊『玄奘三蔵』
2011/11/07
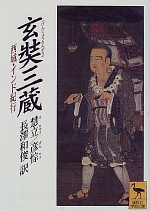 先日紹介した『弓と禅』の極めて内省的な雰囲気とあまりも対照的だったのが、その直前に読んだ『玄奘三蔵』に描かれた玄奘の求法の旅でした。
先日紹介した『弓と禅』の極めて内省的な雰囲気とあまりも対照的だったのが、その直前に読んだ『玄奘三蔵』に描かれた玄奘の求法の旅でした。
この本は、玄奘の死後それほど間をおかずにまとめられた伝記である『大唐大慈恩寺三蔵法師伝』十巻のうち巻一〜五(玄奘の生い立ちから不東の旅に出てインドに遊学し敦煌に帰国するまで)を長澤和俊氏が現代語訳したものです(ちなみに、訳者の著書としては『楼蘭古城にたたずんで』を読んだことがありますが、これもお勧め)。玄奘の辿った旅のルートを確認しておくと、次の図(「平山郁夫 祈りの旅路」の図録から引用)のようになります。ただし、この図はけっこういい加減なところがあって、例えば往路には敦煌は通っていないのですが、だいたいのスケール感を見てとれればよしとします。

なぜ玄奘は、これほどにも長距離にわたる旅を思い立ったのか。当時の中国では、5世紀に鳩摩羅什クマーラジーヴァが伝えた龍樹系の大乗教学にかわって、無着アサンガ・世親ヴァスバンドゥ(興福寺の仏像を思い出します)の「唯識」の教義がインドに遅れること200年でようやく盛んになり始めていました。しかし、仏典の不足する中でさまざまな異説が生じていたために、玄奘はどうしてもインドへ赴き仏教哲学の最高峰「瑜伽師地論」を学んで諸々の疑問を解決したいと決心したのでした。
小説やテレビの『西遊記』の影響もあってか、我々は、玄奘がたった1人か、またはごく限られた人数でこの旅路を辿ったかのようなイメージを持ってしまいがちです。確かに、当時の国禁を犯して出国した玄奘は1人で老馬に乗って河西回廊の乾燥地帯を旅し、あやうく乾き死にしそうな目にあったりもしていますが、玄奘の旅が危難に満ちていたのは実はここまで。なんとか伊吾(ハミ)に辿り着いた玄奘は、そこで高昌国王の招きを受けて高昌国(→上の地図のトルファン周辺。現在の高昌国の様子は〔こちら〕)に1カ月にわたり滞在することになり、そこから大規模な隊商に守られて西へと出発します。当時の中央アジアは西突厥の支配下にあったのですが、高昌国王・麴文泰は西域諸国や西突厥の可汗に対する贈り物と玄奘を保護してほしい旨の依頼状をつけて送り出してくれており、天山山脈の北にある王庭で葉護可汗ヤブクカガンと対面した後は、インドに到達するまで可汗の威令の下におおむね安全な旅を続けました。インドでナーランダー寺を中心に足掛け10年の研究の日々を過ごした玄奘の帰国に際しても、当地のハルシャヴァルダナ王が帰国の手配を全てしてくれています。
このように、玄奘の旅は行く先々で有力なパトロンを見つけ、その庇護の下に旅を続けるというスタイルをとっており、そうであればこそ膨大な経典や仏具を唐に持ち帰ることも可能となったわけですが、そのように次々に庇護を得るための玄奘の武器は、経典の「講義」でした。旅に出る前にすでに大乗・小乗の双方に通じていた玄奘は、高昌国では『仁王般若経』を講義して国王に感銘を与え、葉護可汗の前でも説法を行って歓喜させています。ナーランダー寺で研鑽を積み、外国人でありながら一級の学僧と認められるようになった玄奘はこの大学で衆僧のために『摂大乗論』の講義を行い、ついにはハルシャヴァルダナ王が主催した大法会においてインド中の王、僧、バラモンを前に自ら著した『制悪見論』を講じて熱狂的な歓呼の声を浴びることになります。
ここでもう一度上の地図を見る必要が生じますが、高昌国は唐の言葉がそのまま通じたにしても、葉護可汗の前で用いた言語は(よほど仏教に通じた通訳がいない限りは)トルコ系の西域の言葉であったでしょうし、インドではサンスクリットを自分のものにして高度な論文を書き著すまでに至っています。そうしたマルチリンガル能力と、余人の追随を許さない高い学識をベースにしつつ、センセーショナルな興奮を呼ぶほどの説得力を持って講義をなし得た玄奘は、今で言えば東京ドームを満杯にするほどの人気を勝ち得た世界的スーパースターであったのだと思います。そうした派手なカリスマ性こそが玄奘の本当の姿であって、テレビの『西遊記』で三蔵法師を演じた夏目雅子さんのようなはかなげな存在では断じてないのです。


ついでに言うと、玄奘は旅の途中に有名な仏跡があれば大回りしてでも必ず立ち寄っています。こうした、玄奘の意外にミーハー(?)な姿が垣間見えるのも、この本の面白いところでした。