我等
アイン・ランド『アンセム』
2020/03/13
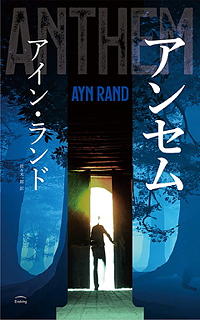 サイエンス・フィクション『アンセム』(〔著〕アイン・ランド〔訳〕佐々木一郎)を読了。
サイエンス・フィクション『アンセム』(〔著〕アイン・ランド〔訳〕佐々木一郎)を読了。
アイン・ランド(Ayn Rand 1905-1982)は、ベストセラー小説『水源』(1943年)と『肩をすくめるアトラス』(1957年)の二作品で知られるロシア系アメリカ人の作家・思想家。個人の理性に依拠する合理的利己に価値を置き自由放任資本主義を唯一の道徳的な社会システムと見なすその思想は彼女自身によって「オブジェクティビズム」と名づけられ、彼女の作品にも反映されているとされますが、この短編小説『アンセム』も例外ではありません。
集団主義・平等主義が極限まで推し進められた遠い未来、個の概念がなくなって自分をさすために「われら」という代名詞が用いられ、かつて人類が獲得した科学や芸術も忘れ去られてしまった世界。主人公〈平等7-2521〉は自分の止め難い知識欲が〈兄弟ら〉とは異なることの罪深さにおののきながらも、偶然に見つけたトンネルの中で〈語られべからざる時代〉の失われた技術(電灯)を再発見します。このことを〈学者世界評議会〉に報告すれば主人公の罪は許され学者の一員になれると信じたのに、学者たちは主人公の発明が反集団主義的な行為であると糾弾し発明を破壊しようとしたため、主人公は〈市〉を脱出して〈地図に描かれざる森〉へと逃走。密かに愛し合うようになっていた若い女性〈自由5-3000〉も後を追って主人公と合流し、2人は森の奥へと歩き続けて遠い過去に建てられた家を発見します。その書庫にあった書物の中から、主人公は「私」という概念を見つけ出して涙し、「自分自身のために生きる自由が一人一人にある世界」を築くために戦うことを誓うところで、本書は終わります。
主人公が密かに書き綴った記録という構成をとる本書はいわゆるディストピアSFの系譜に属する物語ですが、主人公が自分を「われら」と呼ぶことに最初は面食らうことを除けば、主題は明瞭、展開もスピーディーで非常に読みやすい本です。むしろ注意を引いたのは著者前書きで、そこには次の記述がありました。
初版が出版されたとき、この物語を読んで私にこう言った者たちがいる。集団主義の思想を、私はフェアに扱っていない。これは集団主義が説いていることでも、意図していることでもない。集団主義者たちはこんなことを主張しているわけではない。誰もこんなことは言っていない、と。
本書の最初の出版は1938年にイギリスで行われましたが、米国では出版社が見つからず、『水源』がベストセラーとなった後の1946年にようやく改訂版が米国で出版されたという経緯があり、よってこの物語を読んで私にこう言った者たちとは初版の原稿を持ち込まれて出版を拒絶したアメリカの出版社のことだろうと思われます。だとすると、米国において集団主義(=社会主義?)を擁護する空気が当時あったのか、それとも何か別の文脈があったのだろうかと不思議に感じました。
ところで、なぜこの本を読むことにしたかと言えば、先日亡くなったNeil Peartが作詞した「2112」がアイン・ランドの『アンセム』に触発されたものとされているからです。
Rushの初期においてファンから聖典とまで呼ばれ崇められた名盤『2112』(1976年)のA面を全て使った組曲「2112」もまた遠い未来のディストピアの話で、こちらは洞窟で太古の楽器(ギター)を見つけた主人公が喜び勇んで報告したシリンクス寺院の司祭たちに拒絶され、絶望に打ちひしがれながら過去の美しく豊かな文明と芸術の時代の再来を夢想するというストーリー。『アンセム』の中で〈世界評議会の院〉の門にWe are one in all and all in one. There are no men but only the great _WE_, one, indivisible and forever.
と記されているのと同じように、「2112」の司祭たちもIt’s one for all and all for one. We work together, common sons. Never need to wonder how or why.
と高らかに宣言するのです。
他にも、Rushのセカンドアルバム『Fly By Night』(1975年)にはそのまんま「Anthem」という曲があり、その歌詞も自分のために生きること(Live for yourself)への讃歌といった内容ですから、Neil Peartの価値観の根底にはアイン・ランドの主張に通じるものがあったのかもしれません。ともあれ、初めて『2112』を聴いたほぼ40年前にそのライナーノーツで存在を知った本書を、ようやく読むことができて感無量です。